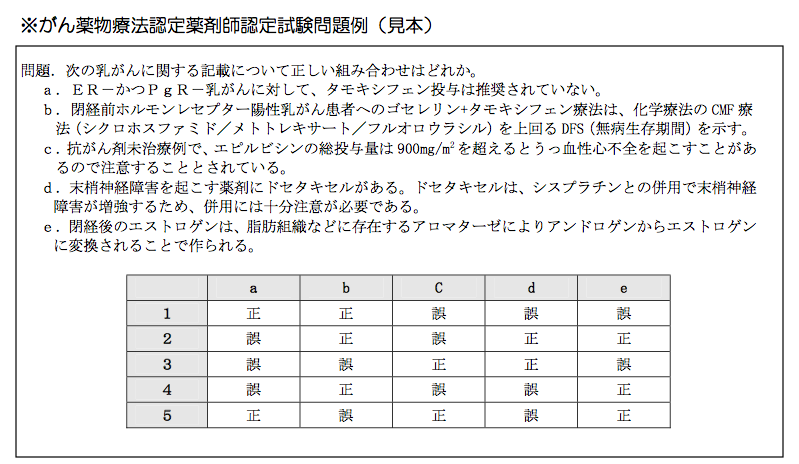これから日本は超高齢化社会を迎え、薬局に求められる機能も今後、変わってきます。当然、薬剤師に求められる能力も変わってくることが予想され、その要求に対応出来ない薬剤師は淘汰されてしまうかもしれません。
今のうちから、変化に対応する準備をしておくことが重要です。 では、具体的に、どんなことが求められるのか?
『薬局業界の動向とからくりがよ~くわかる本』では、これからの薬局に求められる要件として、次のものをあげています。
機能 | 具体的対応 |
医療用医薬品供給 | 処方せん応需、休日・夜間の応需体制、医療用麻薬の供給、無菌調剤の供給 |
医療安全対策 | 処方鑑査・疑義照会の充実、副作用発見・発現防止、長期処方・多剤投与への対応、医療情報の共有 |
セルフメディケーション支援 | 受診勧奨等のトリアージ、一般用医薬品、一般用検査薬、サプリメント等の供給、日常健康管理支援 |
在宅医療・介護 | 地域包括ケアシステムへの参画、在宅医療応需体制、他職種連携 |
よろず相談機能 | 禁煙支援、生活習慣病予防の相談・指導、災害対策、うつ・自殺予防、認知症の早期発見と予防支援、在宅医療・在宅介護の相談応需 |
参照)薬局業界の動向とからくりがよ~くわかる本
この表をみれば、おおよそのところはイメージ出来ると思いますが、調剤だけではなく、健康増進や予防管理、地域の相談役としての役割、在宅医療の支援といったものが、主要な業務になってくるということです。
これらの業務に対応するには、医療や介護に関する幅広い知識を身につける必要がありますし、患者さんとは今まで以上に綿密な関係性を作ることが大切になってくるため、コミュニケーションスキルも必要です。
地域包括ケアシステムへの関与
地域を一つの医療施設、療養施設とみなして高齢者の医療・介護を行っていこうというのが、地域包括ケアシステムという考え方です。
具体的には医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスの5つで、日常生活において適切に提供出来るように医師、社会福祉士、看護師、介護士、ヘルパー、ケアマネージャー、保健師、ボランティアといった様々な業種の人間が連携して、町ぐるみで高齢者をサポートしていくという発想です。
そのなかには、もちろん薬剤師も含まれます。地域包括ケアシステムにおいて、薬局は在宅医療や介護における医薬品の提供や管理、服薬支援を担う役割が期待されています。自宅で療養している高齢者の殆どが薬物治療を受けているため、薬の管理、服薬指導は重要なものとなります。
残念ながら、今現在においては、地域包括ケアシステムに関わっている薬局は、まだ少ないのですが、今後は積極的に関与することが求められるのは必然であり、こういった業務に対応出来る人材に対するニーズが高くなることが予想されます。